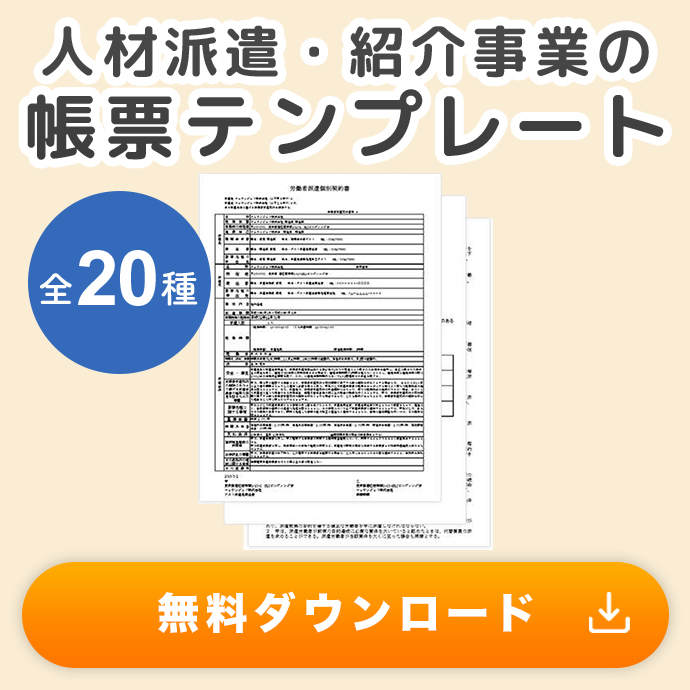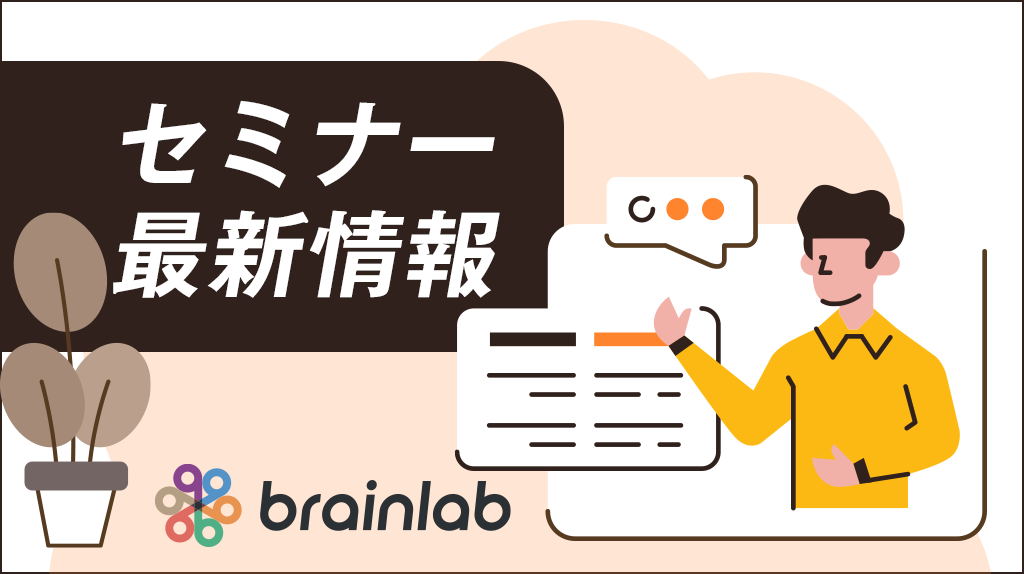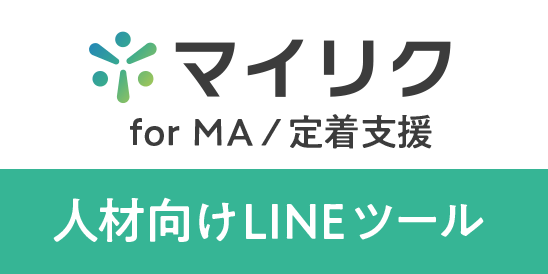「村井満」この名を聞いて、ピンとくる人は、サッカー好きか、バドミントン好きか、あるいは人材ビジネスに明るい人でしょうか。
村井満氏は、日本最大の人材紹介会社であるリクルートエージェントの元代表取締役であり、2014年に、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)第5代チェアマンに就任した人です。サッカー業界は門外漢であったにも関わらず、チェアマンに抜擢されたため、当時は「黒船」などと報道されました。ビジネスの世界から、スポーツの世界へ。そして2024年の現在は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、バドミントン協会)の会長を務めていらっしゃいます。
未経験からくる不安、ビジネスにおける意見の不一致で起こった修羅場……数多くの困難を乗り越えてきた村井氏が、これまでの経験の中で大切にしてきた指針としている考え方があります。それが「天日干し」という概念。一般的な「天日干し」には、雑菌の繁殖を抑えたり、ダニなどの害虫対策にも効果があるといわれています。洗濯物や、布団などを想像すると、わかりやすいでしょう。この考え方や姿勢を、組織や個人に適用しようというのが、村井氏が提唱する「天日干し」の経営、生き方です。
今回、DiSPA!では、この「天日干し」の姿勢こそが、人材業界で働くビジネスパーソン、ひいては人材業界に関わる全ての人にとって、健やかに働き続けるための大きなヒントとなるのではないかと考え、「人材業界における、天日干し経営の効果と、その実践方法」についてお話を伺いました。「個人も組織も“天日干し”で成長する」という村井氏のインタビューを、連載でお届けします。 第1回目の今回は、「天日干し経営」の真髄 – Jリーグ元チェアマン村井満氏が語る組織の透明性と成長の哲学と題し、村井満氏の行動の原点についてお話頂きました。
記者会見71回の真意 。村井氏が貫いた「天日干し」の姿勢

――村井さんが提唱されている「天日干し経営」は関係者の視線につねに身をさらし、「人に言えないことはやらない」という姿勢のことだと理解しています。
「魚と組織は天日にさらすと日持ちが良くなる」。私の口癖です。布団を干せば雑菌や害虫対策になる。魚を干せば保存食になる。それと同じで、組織も「天日にさらす」ことで強く、そして成長する組織になります。天日干し経営とは、多くの人の感性や、意見を交換するための開かれた場の創出のことです。閉ざされた部分を作らない。
この姿勢がトップだけでなく組織全体に行き渡れば、厚いルールブックはいりません。まさに「人に言えないことはやらない」。これが唯一の約束事になり、そこで働く人はみな、自律的で当事者意識が芽生えるでしょう。
天日干しの姿勢で経営を実践していったことで、私はプロとしての選手経験もなければ、監督やコーチなどの経験もないようなまったくの門外漢であったにも関わらず、Jリーグのチェアマンとして、組織に受け入れられ、財政面での立て直しや、2020年からの新型コロナウイルス感染症によるさまざまな困難へも立ち向かえたと考えています。
――トップ自ら、さらされる姿を職員に見せていたということでしょうか。
そうです。例えば、私はコロナ禍が始まった2020年だけで、71回の記者会見を行いました。会見はオンラインで実施しているので、毎回ありがたいことに北海道から九州まで、多いときは300人ほどの記者が参加してくれていました。でも、その71回の記者会見で原稿を用意したことは一度もありませんでした。実直に、現在の判断とそれに至った過程を説明するのに原稿はいりません。コロナ禍の記者会見は天日干し経営の象徴的な姿だったと思います。
試合の開催の是非に関する決定も、チーム関係者や専門家など多くの人と協議し、確認しあいながら進めていました。それら全部を把握できる透明性のある組織作りにしていたからこそ、私は自分の言葉で話すことができたのです。
――記者からの答えられない質問などはありませんでしたか。
もちろん、あります。さまざまな角度から、徹底的に質問攻めにされるのが記者会見ですから、それは全然問題ではありません。むしろ、その質問こそが、さらに天日干しを加速してくれるのです。
つまり、記者のほうから「この情報は認識していないのか」「あのデータは確認していないのか」とご指摘を受けることこそ、天日干しなのです。知らないことは知らないと素直に認め「読んでいません」とはっきり答えていました。逆に、そのように指摘されたことで「そうか、あの資料を読んだ方がいいのか」「その視点でも考えておく必要があったか」などと気付きがあります。記者からの質問や指摘は、これまで欠けていた視点を補ってくれるありがたい言葉です。そんな緊張感のある記者会見を何度も重ねていくうちに、スポーツ観戦における感染症対策についてはかなり詳しくなることができました。天日干しの姿勢でいれば、ものすごく多くの情報を集めることができます。そして、強くなるのです。
――全てを天日(関係者の視線)にさらすというのは、非常に勇気のいることのような気がしています。村井さんは、勇気が出ずに、天日干しの姿勢でいることができないときはないのでしょうか。
天日干しの姿勢は一見勇気が要りそうですが、旨味がわかれば、怖くありません。自分以外の人の視点ほど、助けになるものはありません。私は苦境に陥ったときこそ「ああ、天日干しができていなかったからかもしれない」とか「早く天日に干さなければ」と思うほどです。組織も人も、誰しもが日に当たることでより良くなれると身をもって知っているのです。
発信して自らを天日に干すことから逃げてしまうこともあるかもしれません。自己をさらすためには、傾聴が必要です。その姿勢が取れない時は、逃げたくもなるでしょう。それでもいい。ただ、逃げたことを自己認識しておいてほしい。それができていれば、きっと次につながります。
猛反対されることこそ、重要なこと。反発と反響は比例する

――これまで、村井さんでも逃げ出したくなることはありましたか。
逃げ出したいとは思わなかったですけれど、かつて代表を務めていたリクルートエイブリックの社名を変更したときの反発は大きく、非常に印象に残っていますね。
――反発が大きかったのですね。
社名変更は、自分の苗字を変えるような大きな出来事ですから、当然と言えば当然です。反発が大きいというのはとても大事なことである可能性が高いのです。だから一番力を入れるべきポイントです。
会議の議題は、反対意見が大きい順に並べて、上から順に議論していく感覚です。全会一致で決まることなんて、全員にとってどうでもいいことなんじゃないかな。
社内に反発が大きく渦巻くということは、多くの人が当事者意識をもっているということでもあるので、ありがたいことですよね。反発の大きさは、そのまま、その企業や組織の成長を左右する非常に大切な課題だということです。
――たしかに、あの社名変更から、実際に人材紹介業という業界が確立され、今ではエージェントという単語が紹介会社の代名詞になっています。
人材紹介業の確立。これは絶対に必要だと思ったので、どれだけ反対されてもやりきりました。私は2004年に人材紹介会社の「リクルートエイブリック」の代表に転身しました。それまでは、新卒で入社したリクルートで人事担当役員をしていたのですが、「事業の現場に出たい」という念願かなってのことでした。
今では「人材紹介会社」は多くの方に認知されていますが、当時は派遣事業と混同されることも多かった時代です。まだ転職市場が成熟していなかったとはいえ、エイブリックは転職支援の業界ではシェアは6割を超えていました。業界で圧倒的な1位の座を確立している会社としての使命は、業界全体をけん引することです。ですからまずは、派遣業と混同されてしまうような人材紹介業の認知を浸透させなければと思ったのです。
そこで考えたのが社名変更です。当時、リクルートの転職メディアの『とらばーゆ』や『ガテン』などは、知名度が非常に高く「とらばーゆする」「ガテン系」のように、社会に一般名詞のように溶け込んでいました。しかし、「エイブリック」はそこに至っていなかった。社名を変えて、日常会話に出てくる単語となりたい。それで「リクルートエージェント」に2006年に社名変更しました。
経営観が合わない当時の役員間にも非常に大きな葛藤がありましたが、やらなければならないことだと確信していました。
幸いにも狙い通り、「エージェント」は日本において人材紹介業の代名詞になりましたし、転職支援のサービスも一般的になりました。当時は、Googleで「エージェント」と調べると2件しかヒットしなかったのです。それが1年後には200万件、2023年には14,000件にまでなっていて、非常に感慨深かったですね。
※現在はGoogleは検索数を非表示にしています。
緊張感が人を成長させる。バドミントン日本代表にかけた言葉

――村井さんのお話を伺っていると、自らを天日にさらす勇気、そして反発や反対意見も丁寧に傾聴したうえで、信念をもって進める行動力こそが、成長に必要な要素だと感じました。
もうひとつ付け加えるとしたら、人が成長するには、緊張感が必要です。緊張感は、人を成長させるのです。考えてみてください。最初は10人の前でしゃべるのにも緊張していた人も、慣れていきます。そうすると次は20人の前だと緊張するようになり、横浜アリーナの2万人の前になり…と緊張の大きさが変化します。緊張感が高くなる事こそ成長の証です。
私は「緊張する方を選ぶ」ことを、天日干しの姿勢と同じくらい大切にしています。人は自分にできるかどうか、ギリギリのところにチャレンジしているから緊張するのです。逆に緊張しなくなったら、それは成長が止まってしまう予兆です。だから、どんどん大きな緊張を引き受けていくしかない。
もし緊張している自分を自覚したら、「まだ緊張しているのか」と自己嫌悪になるのではなく、「こんなに成長したのか」とポジティブにとらえてください。私なんかは緊張がなかった日などは「今日は緊張しなかったな、ダメだな」と反省するくらいです。
2024年パリオリンピックのバドミントン代表の選手への激励の言葉は、まさにこの話でした。「みんな、緊張するよね。でもこんな大きな舞台で緊張できるって、それだけ成長しているってことだ」と伝えて、送り出しました。
――緊張は成長への道しるべですね。パリでのバドミントンの選手たちの粘り強さの根底にあるものが何かわかった気がします 。ありがとうございました!
第2回では、天日干し経営の視点でみる、組織の理想的な在り方として、評価制度やミスが起きたときの対処法などを伺います。マネジメント層の皆さんはもちろん、スタッフ層の方々にも勇気をもらえる内容です。併せてお楽しみください!
プロフィール
村井 満(むらい みつる)
第5代Jリーグチェアマン/日本バドミントン協会会長
1959年埼玉県川越市生まれ。1983年早稲田大学法学部を卒業後、日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)入社。営業部門を経て、同社人事部長、人事担当役員。2004年から2011年まで日本最大の人材紹介会社リクルートエージェント(現リクルート)代表取締役社長、2011年に香港法人(RGF)社長、2013年に同社会長に就任。2014年にサッカー界以外から初の起用となる公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)第5代チェアマンに就任。DAZNと10年間2100億円の配信契約を締結するなど財政基盤の立て直しをはかる。2019年には年間入場者数が過去最多を更新し、クラブとリーグの合計収益も過去最高を記録。2020年からの新型コロナウイルス対策ではNPB(一般社団法人日本野球機構)と連携し、迅速な対応で日本のスポーツ界をリードした。4期8年にわたる任期を終え、現在はJリーグ名誉会員、公益財団法人日本サッカー協会顧問、2023年より公益財団法人日本バドミントン協会会長。JOC理事。