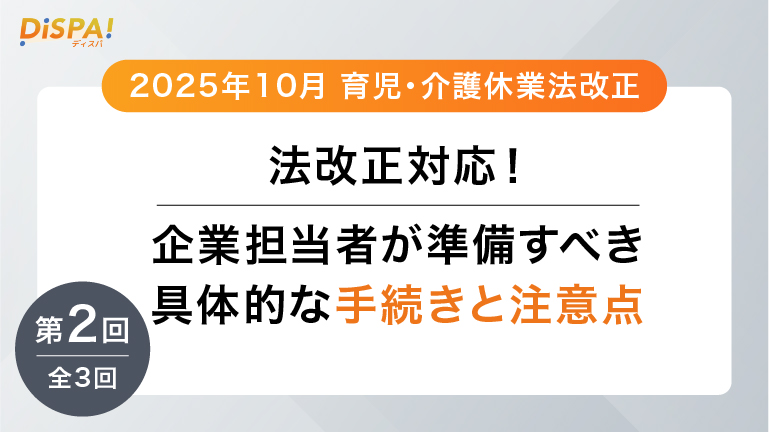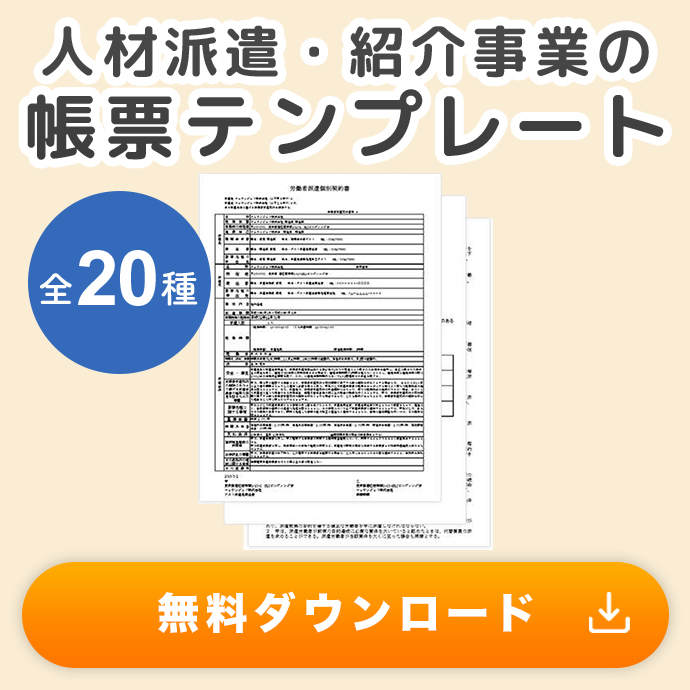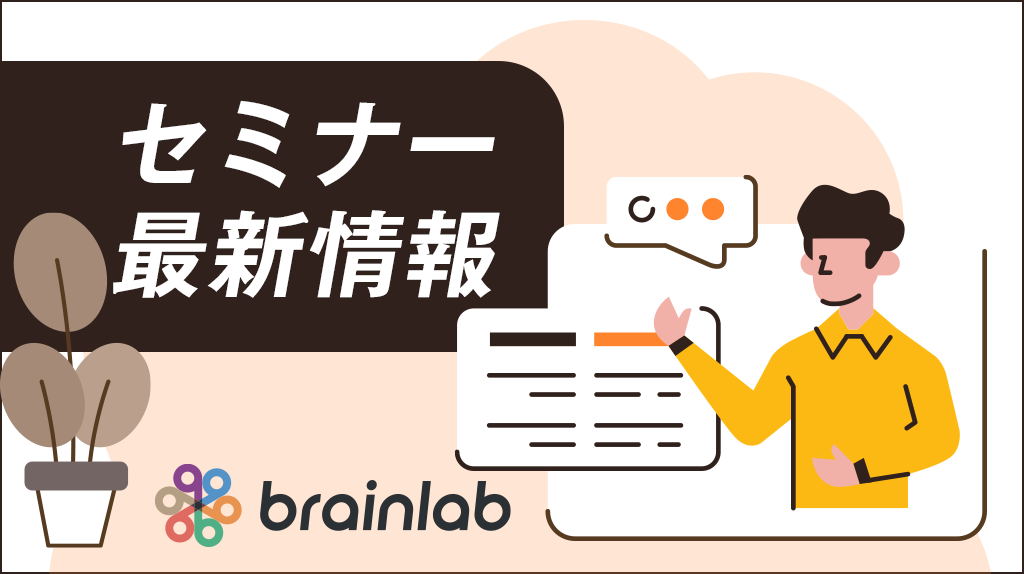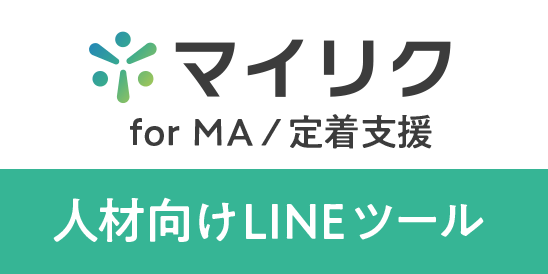前回の記事では、2025年10月1日からの育児・介護休業法改正の概要について解説しました。今回は、その改正内容を企業としてどう具体的に対応すべきか、人事・労務担当者が準備すべき具体的な手続きと実務上の注意点を解説します。
企業が取り組むべき3つの具体的な法改正対応
2025年10月の育児・介護休業法改正をスムーズに乗り切るために、以下の3つのポイントを確実に実施しましょう。
就業規則等の見直し
従業員が利用できる2つ以上の措置(例:テレワーク、短時間勤務制度など)を選択し、就業規則に反映させることが義務付けられています。
また労使協定を締結して入社1年未満の有期雇用契約社員を対象から除外している場合は、労使協定を訂正して再締結する必要があります。
入社1年未満の有期雇用契約社員を除外している派遣会社は多いと思われますので労使協定の再締結も忘れないようにしましょう。
<実務担当者はここに注意!>
措置を選択する際には、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。労働組合がない場合は、36協定のように労働者の代表から意見聴取します。
個別の周知・意向確認体制の整備
法律で定められた時期(妊娠・出産等の申出時や、子が3歳になる前の適切な時期)に、制度の内容などを個別に周知し、利用の意向を確認するための体制を整えましょう 。
<実務担当者はここに注意!>
従業員への面談や書面交付、オンライン面談などの方法で、個別の周知と意向確認を行うための体制を整えることが重要です 。
また従業員に対し、制度の利用を控えさせるような不適切な言動がないよう注意が必要です。
相談窓口の設置
従業員が育児や介護に関する悩みを安心して相談できる窓口を設けることが望ましいです。
企業が押さえるべき実務上の注意点
ここでは、制度をスムーズに運用するために、人事・労務担当者が特に注意すべき点を掘り下げます。
- 継続的な対話と柔軟な対応
意向聴取は、法律で定められた時期だけでなく、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」など、状況の変化に応じて定期的に行うことが望ましいとされています 。 - 個別の事情への配慮
子どもに障害がある場合やひとり親家庭の場合など、個別の事情に応じて、短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用可能期間や付与日数に配慮することが望ましいとされています。
まとめ:2025年の改正育児・介護休業法をスムーズに進めるには?
今回の改正は、柔軟な働き方の選択肢を広げ、企業が従業員の育児や介護の状況に寄り添うことを一層求めるものです 。単に法改正に対応するだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整えることが、優秀な人材の確保や定着にもつながります。
- 就業規則等の見直し
2つ以上の措置を選択し、就業規則等に反映させましょう。 - 個別の周知・意向確認体制の整備
従業員への面談や書面交付などの方法で、制度の周知と意向確認を個別に行うための体制を整えましょう。 - 相談窓口の設置
従業員が安心して相談できる窓口を設けることが望ましいです 。
法改正への対応をスムーズに進めるために
法改正への対応は、人事・労務担当者にとって複雑で多岐にわたります。
本記事では概要を解説しましたが、さらに踏み込んだ実務対応や、個別ケースへの対処法についてお困りではないでしょうか?
当社のホワイトペーパーでは、以下の詳細な情報を網羅しています。
- 法改正への具体的な対応手続きと注意点
- 企業担当者が抱きやすい法改正への疑問に関するQ&A集
- 改正ポイントの全体像をまとめたチェックリスト
>>法改正への準備を万全に!【2025年育児・介護休業法改正対応ガイドブック】無料ホワイトペーパーはこちらから
【人材派遣会社の担当者様へ】
法改正対応と同時に、日々の煩雑な業務も効率化しませんか? 「MatchinGood」は人材派遣・人材紹介を一元管理できる業務管理システムです。
求職者・求人、契約管理、法改正対応はもちろん、勤怠管理、給与計算、請求書発行といったバックオフィス業務を自動化します。
>>関連記事を読む
第1回【2025年育児・介護休業法改正】企業が押さえておくべきポイント
第3回【2025年育児・介護休業法改正】育児・介護両立支援制度の全体像