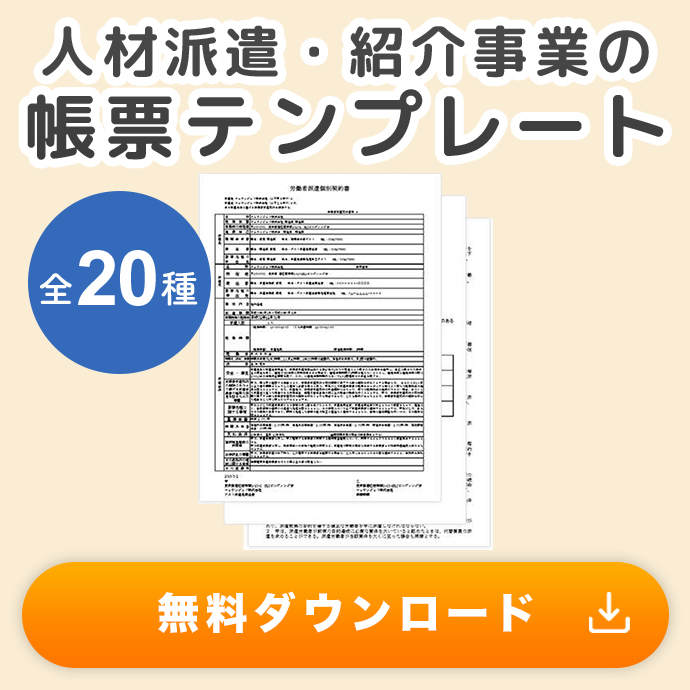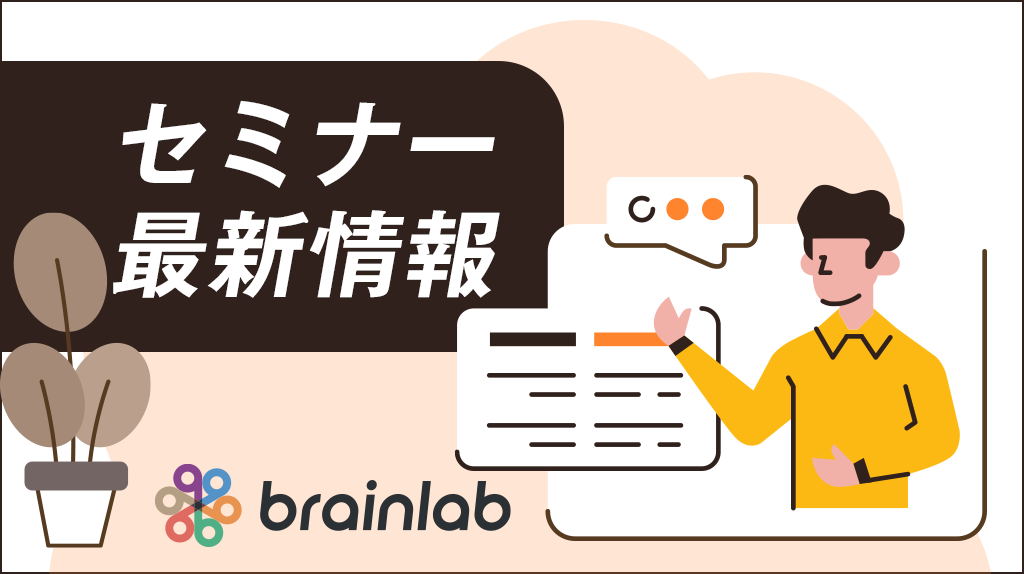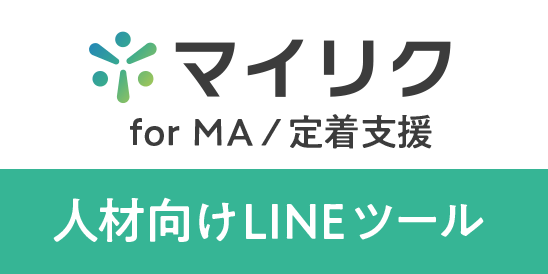東大・松尾研発AIベンチャーCEOが語る、人材紹介会社が生き残るための人とAIの協働戦略とは
人材紹介業界は今、歴史的な転換点に立っています。AIの急速な進化により、従来の属人的な業務プロセスが見直され、より「人間がやるべき」仕事に集中できる環境が整いつつあります。
この変革の最前線で活躍するのが、東京大学・松尾研発スタートアップ®︎の株式会社ACES代表/CEOの田村浩一郎氏です。同社が開発する「ACES Meet」は、オンライン商談・面談の録画・文字起こし・分析を自動化し、営業プロセスのDXを実現するAIツールです。
日本のAI研究を牽引する松尾研究室で博士号を取得し、現在は企業独自の知見を取り込み学習する「エキスパートAI」の社会実装に挑む田村氏に、AIと人材紹介業界の未来像を伺いました。
汎用AIは「優秀な新卒」、真の競争優位は「エキスパートAI」にあり
ーまずは田村様の経歴と、事業に込めた思いをお聞かせください。
田村氏: 東京大学の松尾研究室で学部から博士課程まで在籍し、博士号を取得しました。松尾研ではAIの基礎研究に携わっていましたが、優れた技術があっても社会になかなか届かないという課題を感じ、テクノロジーの社会実装に取り組みたいと考えるようになりました。
そこで2017年11月に、松尾研のメンバー3名を含む6名で共同創業したのが 株式会社ACESです。営業支援AIツールを開発・提供しています。そして現在、特に力を入れているのが企業独自の知識・ノウハウを学習した「エキスパートAI」の開発と提供です。
昨今のChatGPTブームで注目を集めている汎用AIは、インターネット上の知識は豊富で、基本的なことは何でもこなせます。例えるなら、「非常に優秀な新卒社員」。しかし、これだけでは企業の真の競争力にはなりえないでしょう。
真の競争優位性は、顧客一人ひとりのことをどれだけ深く知っているか、社内に蓄積された独自のナレッジをどれだけ使いこなせるかにあります。 これまで、そのような企業のノウハウは、ベテラン社員に蓄積されてしまっていました。しかし、それでは属人的であり、提供するサービスにムラが出てしまいます。そこで我々が目指すのは、企業独自の知識・ノウハウを「エキスパートAI」として実装し、人とAIの協働を実現することです。つまり、お客様のことを最もよく知る「経験豊富なベテラン」のようなAIを各社にご提供するということなのです。

コロナ禍が生んだ歴史的チャンス「ミーティングのデータ化」
ー 「エキスパートAI」の実装のためのツールが「ACES Meet」ですね。開発の経緯を教えてください。
田村氏: コロナ禍で、Zoomでの面談や商談が一気に当たり前になりました。これは、これまで属人化し、デジタル化から最も遠い場所にあった「ミーティング」という領域が、一気にデータ化の波に乗った歴史的な転換点でした。
我々はこれを大きなチャンスと捉え、会議シーンを可視化し、AI・ソフトウェアで業務効率を向上させる「ACES Meet」を開発、サービス提供を始めました。目的はシンプルで、ミーティングの「生産性」と「資産性」を最大化することです。
特に人材紹介業界では、候補者の人生を左右する「面談」や、企業の売上を支える「商談」は、企業の競争力に直結します。ここのクオリティを上げるために、やるべきことは何でしょうか。それは、人間でないとできない、表情や声色といったところに表れる、感情に配慮した丁寧なやり取りだと考えました。話に集中するためには、事務作業はできるだけ手放せるに越したことはありません。「ACES Meet」があれば、面談や商談が終わった瞬間に、自動で議事録が完成しています。これまで担当者が手作業で行っていた文字起こしや報告書作成といった作業が不要になり、その分の時間を、候補者との対話や企業のニーズ把握といった本来の業務に集中できるようになります。
-1024x576.png)
さらに重要なのは、これまで「あの時、候補者が何と言っていたっけ?」と記憶に頼っていた情報が、すべてデータとして蓄積されることです。過去の面談内容を検索したり、成功パターンを分析できるようになります。「ACES Meet」は、そうした価値を提供するために開発しました。
ACES Meetが実現する「学習する議事録」の威力
ー 他の文字起こしツールとの違いは何でしょうか?
田村氏: 汎用AIを単に繋げただけのツールとは一線を画します。例えるなら、議事録を頼む相手が「この人誰だっけ?」と思いながら作業する「新卒社員」なのか、参加者の顔と名前、これまでの経緯も全て把握している「数十年の経験を持つベテラン」なのかの違いです。
価値のある議事録にするためには、“誰が話したか”を正確に把握することが不可欠。 「ACES Meet」は、話者認識機能に強みがあり、使えば使うほど「この声はAさんだな」と正確に識別するようになります。
さらに重要なのが、業界特有の言語の理解です。例えば、文脈なしに新卒社員が「CA」「 RA」と聞いても意味が分かりませんが、ベテランなら人材業界の用語だと即座に理解できます。我々は、「CA(キャリアアドバイザー)」「RA(リクルーティングアドバイザー)」といった人材業界固有の用語を高い精度で理解するよう、特化したチューニングを施したモデルを提供しています。
さらに、SaaSでありながら各社固有の専門用語や社員名を登録・学習させる仕組みも構築しており、コストを抑えながら現場に最適化されたAIを育てることを可能にすることができました。

トップセールスの「暗黙知」を数値で完全可視化
ー実際の導入効果について、具体的な事例を教えてください。
田村氏: ある保険会社で、トップセールスと平均的な営業担当者の商談を「ACES Meet」で解析したところ、決定的な違いが数値で可視化され、これまでは分からなかった成功法則が見えてきたのです。成功する商談で重要だったのは、なんと「相槌」の種類と回数でした。
トップセールスは平均的な営業担当者に比べ、顧客との対話における相槌の回数が数倍にものぼり、その種類の豊富さも2倍以上あったことがわかりました。
この「暗黙知」であったトップセールスのスキルを、我々は統計データとして完全に可視化することができました。そして、その結果を新人研修のロープレやオンボーディングに活用することで、組織全体の営業スキルを底上げするPDCAサイクルが回り始めています。
人材紹介業界の課題。2%のマッチング率を打破する鍵
ーこの手法は人材紹介業界にも展開できるのでしょうか?
田村氏: もちろんです。保険営業と同じように、ベテランCAやRAの会話術などを可視化することで、組織全体のスキルレベルを底上げできるでしょう。
でも私は、それだけではなく、人材紹介業界においてはもっと根本的な課題解決にもつながると考えています。現在、人材紹介業界では大手でもマッチング率は2%程度に収束してしまっています。なぜだと思いますか? それは、今まで、構造化できる情報ばかりでマッチングしてしまっていたからだと、我々は考えています。履歴書に書かれているような年齢、学歴、経験年数など、構造化されたデータでしかマッチングできていなかったのです。
しかし、CAが面談で引き出した候補者の本当のWill(意志)や、RAが掴んだ求人票の裏にある企業の真のニーズといった「非構造データ」こそがマッチングの質を左右する、価値の源泉です。「ACES Meet」でこれらの一次情報をリッチなまま構造化しマッチングに活用することで、業界全体の生産性とマッチングの解像度を飛躍的に高める取り組みが既に始まっています。
これまで解析できていなかった暗黙知の部分を可視化することで、人材紹介の仕事はより“転職者ファースト”となり、マッチング率も向上するのではないでしょうか。

AI時代、人間に託される「2つの仕事」
ーAIが業務を変革していく中で、CAやRAの仕事の内容も大きく変わりそうですね。そのような時代に人間がやるべき仕事とは、どのようなことだと考えていますか?
田村氏: AIがベテランレベルの知識を持って業務をこなすようになると、最終的に人間にしかできない仕事は2つに絞られる、と私は考えています。
1つは、「Will(意志)を持ち、意思決定し、その結果に責任を持つこと」です。 AIは最適な選択肢をA, B, Cと提示してくれるでしょう。しかし、最終的に「Bで行こう」と決断し、その未来にコミットするのは人間の役割です。候補者に対し、「私はあなたにBの選択肢が良いと思う」と、その人の人生を一緒に背負う覚悟を持って伝えられるか。これがAIには決してできません。
そしてもう1つは、「知能(インテリジェンス)を、人を動かすエネルギーに変えること」です。 AIがこれから人間より10倍、100倍賢くなることはほぼ確実です。しかし、その知能自体が人の心を動かし、行動を促すことはできません。AIが導き出した最善の知見を人間が理解し、候補者の気持ちに寄り添い、「最後の一歩」を踏み出すための背中を押してあげる。このエモーショナルな価値提供こそが、人間の介在価値になります。
これからのCAやRAの仕事は、AIを最高の相棒として、この2つのコア業務にますます特化していくでしょうし、これこそが企業競争力に直結するのではないでしょうか。
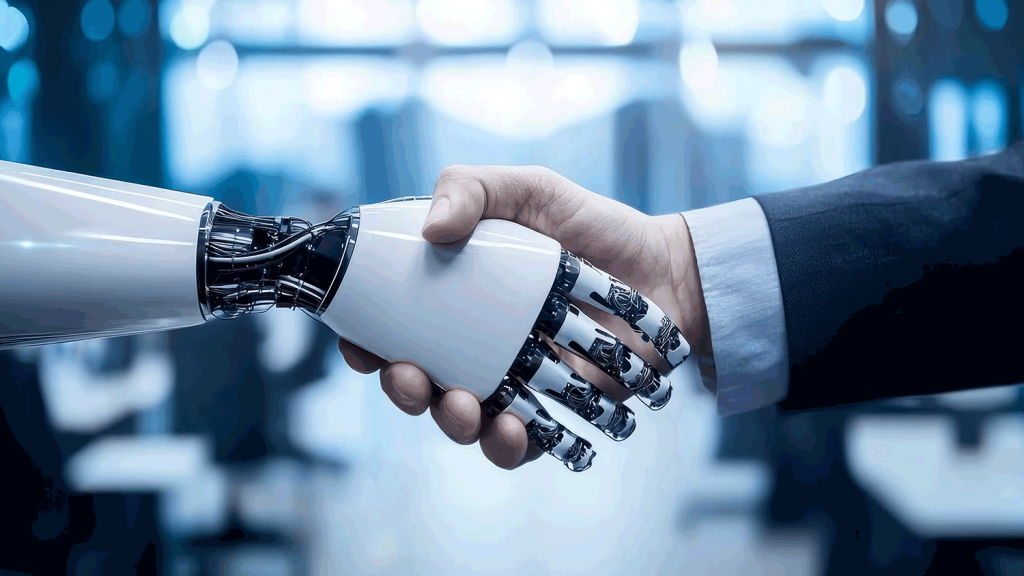
恐れるべきは「AI」ではなく、「AIを使いこなす競合」
ーAI活用にまだ踏み出せていない人材紹介会社へのメッセージをお願いします。
田村氏: よくセキュリティや個人情報保護への懸念を伺いますが、我々のような専門企業が、安全に利用できる環境を高いレベルで用意しています。懸念点がある場合は、まずは専門家に相談してみてください。
もうお判りかもしれないのですが、AIを活用するかしないかという判断で、とてつもない差が出てきてしまう。「AI vs 人間」という構図は間違いだということを強調しておきたいですね。これからの競争の本質は、「AIを武器にした競合他社との戦い」なのです。 自分がやらなくても、ライバルは必ずAIを活用して生産性を上げ、より質の高いサービスを提供してくる。その状況でも、使わないのですか? と問いたいのです。
AIは敵ではなく、人間がやるべき本質的な仕事に集中させてくれる相棒のような存在です。今までは、業務に時間がかかってしまい「自分はなぜこの仕事を始めたのか」「どのような人を支援したいのか」などという初心や信念を思い返すこともできなかったでしょう。しかし、AI時代に必要になってくるのは、まさにこの初心や信念の部分です。人間にしかできない仕事に集中するためにも、積極的に取り入れる姿勢を持てると良いのではないでしょうか。
まとめ:人材紹介業界の新時代が始まる
株式会社ACES CEOの田村氏へのインタビューから見えてきたのは、単なる業務効率化に留まらない、人材紹介業界の新たなパラダイムシフトでした。
重要なのは、この変化は「もうすぐ来る未来」ではなく、「今まさに起きている現実」だということです。 田村氏の言葉通り、競合他社はAIを活用することで、社員全体のパフォーマンスを向上させ、より精度の高いマッチングを実現している可能性があります。その一方で、自社が従来の手法に固執すれば、その差は取り返しのつかないものになりかねません。
「人のキャリアのことを、AIに任せるなんて」という声も聞こえてきそうですが、実際は逆だということが、今回のインタビューで明らかになりました。AIを味方につけることで、CAとRAが本来やるべき「意思決定と責任」「人の心を動かすこと」に集中できるようになります。事務作業から解放されることでできた時間を、候補者一人ひとりの人生と真剣に向き合い、企業の本当のニーズを深く理解するために使えます。そんな「人間らしい価値提供」こそが、今後ますます重要になっていくのでしょう。AIを取り入れることで、人材紹介会社はもっと質の高い出会いを生み出し、業界全体がさらに前向きに成長していくーーそんな希望を感じるインタビューでした。
プロフィール

田村 浩一郎 氏
株式会社ACES
代表取締役/CEO
東京大学大学院工学系研究科卒(工学博士)。松尾研究室で金融工学における深層学習の応用研究に従事。Forbes 30 Under 30 Asia 2022 Enterprise Technology部門に選出。2017年、「アルゴリズムで社会はもっとシンプルになる」というビジョンを掲げ、株式会社ACESを創業。「松尾研発スタートアップ®︎」に認定される。アカデミアと事業の接合を意識し、会社を経営しながら自らも博士号を3年で取得した。AIアルゴリズムを前提にした働き方・産業はどのような姿かという問いを立て、AIの社会実装を率いる。