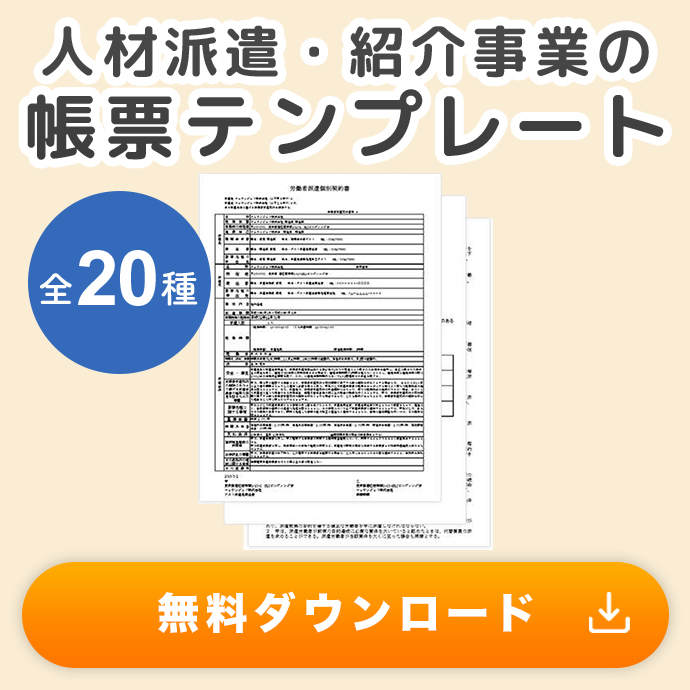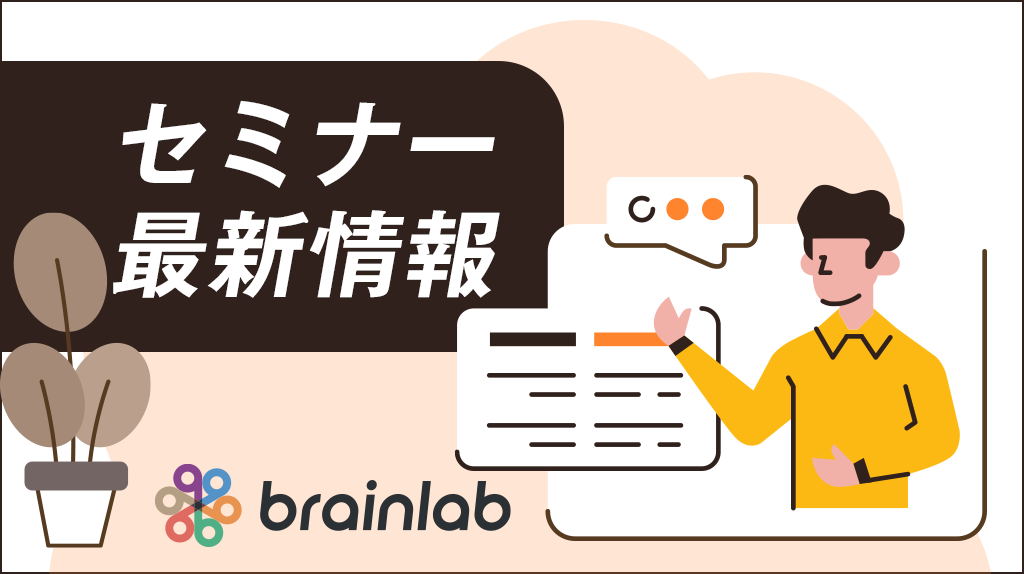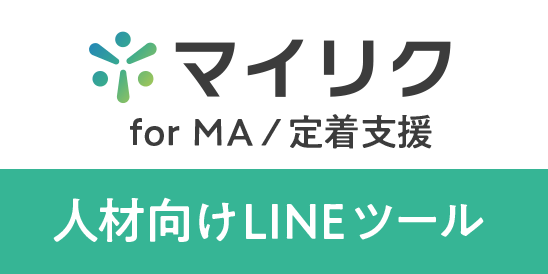人手不足が叫ばれる労働市場において、いかに人材を確保していけるかが企業の今後の命運を左右するとも言われています。採用トレンドもスピード感を増しながら変化し続ける今の時代、誰もが人材マーケットの動向に目を光らせる必要があります。
キャムコムグループの一員である(株)天職市場において、アナリストチームで活躍されているチーフアナリストの斎藤一氏に、労働市場データ分析の重要性や、その活用方法、今後のAIとの関わり方など幅広いお話をお聞きしました。
アナリストチームとして、ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用
ーまず斎藤さんの行なっておられる業務内容、役割などについてお話いただけますか?
私は株式会社天職市場のアナリストチームのチーフアナリスト、リーダーをやっています。天職市場の主な業務は、伴走型採用支援サービスとして、求人広告の運用改善を行っています。また私は、お客様には手元の採用活動のデータだけでなく市場の動きも知ってほしいと考えており、採用市場のトレンドやデータ分析等の情報提供をしています。
ー斎藤さんの所属しているアナリストチームについてもお聞きできますか?チームの狙い、役割などについて。
まず、天職市場の元々の価値は何かというと、求人メディアや検索エンジンの広告運用が一つありました。ただ現在は、昔のように費用対効果をうまく回していれば応募が多くなるというわけではなく、求人内容に関してターゲット層の方たちが知りたい情報ときちんとマッチしているかどうかが重要になっているのです。今はどのメディアもマッチした人に求人案内を出す形になってきていて、尚且つどの求人が当たったかを分析して運用する、私たちのバリューはそこにあると思っています。
お客様個別のサポートでは、データを分析して、お客様と求人一件ごとに改善しています。ただそのままですと、手元のデータのみの分析でしかない。一方で世の中の流れはこんな変化しているよ、という部分はわからないんですよ。労働市場はどうしても法律に一番影響を受けるところですし、また最近のSNSのトレンドキーワードなどにもかなり影響を受けたりします。過去から今はどうなのか、この先はどうなるのか、それら全てを見据えながら、マクロなデータ提供を行なっていかないと、ただ現場で一生懸命やってるだけで終わってしまう。そういったミクロとマクロ、両方の情報提示が必要だと思っています。
ー人材ビジネス業界でアナリストチームがあることは結構珍しいのではないでしょうか?
そうですね。大手の人材会社さんにはありますが、なかなかないかもしれません。アナリストチームの立ち上げのきっかけも、元はお客様発とも言えるんですよ。例えば、お客様から一番聞かれる相談の一つに「求人はどの時期に出すのがいいか」というものがあります。一般的なイメージの求人広告は、ある期間掲載して、そのタイミングで応募があるかないかですよね。そこをストレートに知りたい、と尋ねられました。実はこうした内容は、昔は求人メディアといわゆる太客の間でしかなかった話。それが今の時代になり、幅広く色々な情報提供が当たり前になってきているんです。当社のようなお客様の要望をダイレクトに聞く求人広告代理店、求人メディア運営会社、そしてお客様の採用サイトも作成するような伴走型サービスの会社として、きちんとマーケットの情報をお伝えすることは、必要な役割だと思います。上手な求人広告の作り方、出稿のタイミング、求職者は本当は何を考えているか、そういった情報の深掘りをしてあげて、お客様の声に応えたいというところから、アナリストチームも始まったと言えますね。 採用のトレンドに関しても、昔は紙媒体のタウンワークなどに載せればよかった、それがWeb版のタウンワークになり、さらに今やスマホであらゆる情報の中から必要な情報だけが出てくる時代です。こういった変化については誰かがきちんと伝えるべきだと感じています。ただ、業界全体としては、まだ十分に情報提供ができているとは言えない状況だと思います。

時代に合った発信方法でお客様に最適な提案を
ーさまざまなデータ分析を行いつつ情報発信もされている中で、実際に現場の関心が高い課題やテーマとして、どんなものがありますか?
最近ですと、お客様から、自社の社員向けに集中セミナーをやってほしいというお声がけをいただきました。本来はそうしたサービスは行なっていないのですが、現場で悩んだり困ったりしているならばぜひお手伝いしましょうと。そこでは新卒採用に苦戦しておられたため、新卒市場の現況や課題など、データ単体で見ることの他に、最近の若年層の考え方や傾向・トレンドといった広い視点から見てみることもすごく大事だとお伝えしました。
また、とあるセミナーでインターンシップの話をしていたところ、新たに、ある企業団体から会員企業向けにセミナーをやってほしいという依頼がありました。そちらでは最終的に年間通して6回のセミナーを開催しました。新卒採用やインターンシップなど、若い方の採用に関して困っているといった共通点を、多くの企業様が抱えておられます。今の時代、若年層の採用という課題があるのだと実感しました。
ーセミナー登壇も積極的に行われているのですね?
セミナーは昨年(2024年)は31本。月に3本近く登壇しています。基本的には既存のお客様への情報提供が中心ですが、社会課題やトレンドをテーマにしたセミナーを精力的に開催しているので新規のお客様にも伝える機会が増えています。共催型のセミナーへの登壇依頼も、非常に多くなっていますね。
セミナー用の情報収集や資料作成など、どうしても時間はかかります。ただそれだけ知見が溜まっていくわけですので、その情報をYouTubeのチャンネルでお話しするなど、ニューメディアを利用して伝えています。

ーYouTubeも運営されているのですね?
「天職市場チャンネル」という当社の公式チャンネルを運営しています。これまでにショート動画は60本以上、最近は長尺動画に注力しつつあって、月に2〜3本くらいアップしています。長尺動画は、以前はセミナーの抜粋を上げていたのですが、今は当社の社員たちと作成したインタビュー動画を上げています。今後はゲストなどを迎えて、情報提供の中身もさらに充実させていく予定で、すでに企画が進んでいます。
昨今は、60〜70代くらいの経営者の方々も、「先日YouTubeであの話題をを見たよ」といった話をされるケースが増えています。スマホで見たりすることも結構あるようで、情報発信側としては様々なメディアやツールでより良いものを想定しておかなければならないと思います。シニア世代は「ニュース=テレビ」という先入観があると思われがちですが、だんだんとYouTubeに切り替わっているイメージです。民放のニュース番組も、あるニュースを単体で切り取って動画にしていますし、それを皆さん結構ご覧になっているんですよね。ですから今後、例えば一つのテーマで10〜15分、ニュース型で解説するような動画展開などを考えています。
ーセミナーやYouTubeの他に、情報発信のツールとして何か利用していますか?
営業担当がドアノックツールとして活用していた紙面のニュースを5年前から発行していて、現在では発刊66号を迎えています。時代が変わって、紙の配布から今はデータダウンロード形式になっています。提供方法は変われども、初回発行時から今でもコミュニケーションツールとしての役割は変わっていません。
ー最近はどんなニュースを掲載されましたか?
最近ですと物流2024年問題の話や、育児介護休業の件、求人のメディアの祝い金禁止など。こういった制度改正の影響などの解説は、適切にお伝えするようにしています。そしてもう一つ、AI活用に関する話題は要望があるので取り上げています。

AI活用の先にある人材サポートの未来像
ーAIの話題も注目度が高いのですね?
少し前は「ChatGPTで求人票作成はできるんですか?」といった質問が多かったのですが、今は「ChatGPTで作った求人票でどれくらい応募者獲得できますか?」といった具合です。リテラシーが高くなりAIを使えるようになった方が、AIの精度が確かなのかどうかを検証する段階、あるいは実践段階に入ってきているのです。個人のパフォーマンスを上げることに関してはある程度定着してきている中で、それを前提として組織的に活用していくのか、あるいはさらに効率よく効果検証するにはどうするのか、一歩踏み込んだフェーズに来ていると考えています。AI面接やAIマッチングの話題が増えてきているのはその一つの現れだと思います。
ーAIがエージェントや人材派遣の営業の役割を代行して、応募者と接する時代も遠くはない?
今やAIは雑談もできますからね。実際には自分と対話していると言えるかもしれませんが、コミュニケーションのパターンが非常に豊富になっているので、正確な話でなければ十分雑談程度は可能ですよね。ただ、仕事探しの場合はもっと深い部分での悩みや葛藤があり、人間が相対しても難しいことがあります。
AIに代替されにくい人間ならではの価値として、「信用できること」と「おせっかいなこと」の2点があると思っています。
まず、「信用できること」については、現在のところAIは接客などに使われておらず、信用されていません。そのため、「仕事紹介については人間の方が信用できる」と考えられています。しかしAIが普及し、技術的に信頼性が高まると、人間の介在価値が代替される可能性もあります。
次に、「おせっかいなこと」については、現在のAIは当事者本人からの問いかけやアクションがないと答えを返しません。ですから積極的なアプローチが求められる場面では、AIよりも人間の方が優れています。人材紹介エージェントは紹介成約しないと収入がないため、AIよりも積極的に動く必要があります。また、AIは利用者の希望に合わせて仕事を探すことはあっても、本人に向いていると思う仕事をオススメすることはほとんどありません。このような点は、しばらくの間、人材紹介エージェントの強みとして残ると考えられます。
もしそういった部分までAIが対応可能となれば、人材サービスにとってかなり大きな革命になる、そんな可能性はあると思います。
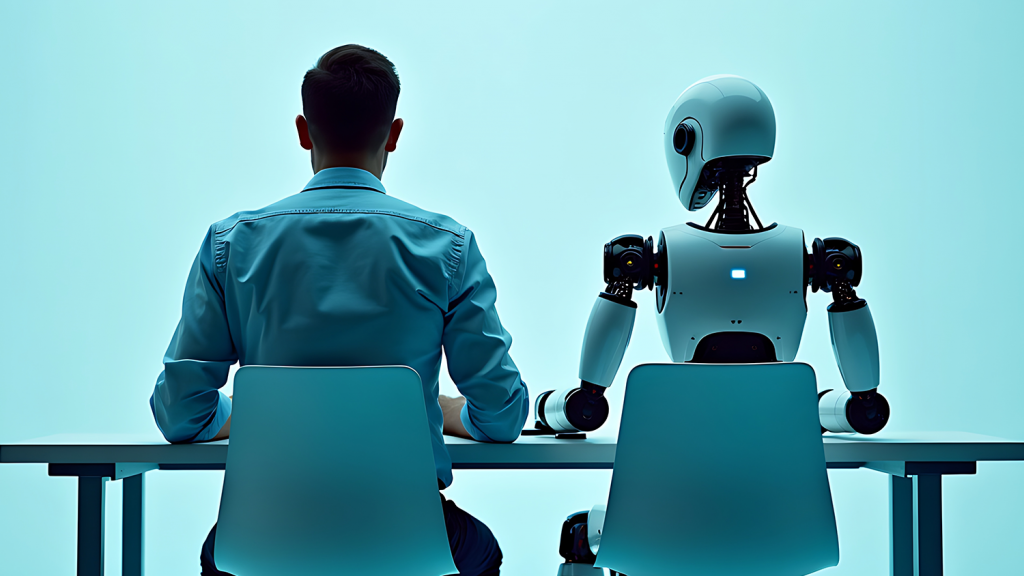
キャムコムグループの一員として人材サポートの役割を果たす
ー改めて、キャムコムグループの中の天職市場という形で、グループ内での連携や今後の展望などをお聞かせください。
キャムコムグループとしては全部で14社です。2001年の設立で、元は地方発の人材派遣会社でした。地方発で全国規模に成長したのは、他にあまりないと思います。地方の製造業や物流業などのお客様に昔からご利用いただいていて、天職市場のお客様もそうした業界の方が多いです。
天職市場として行なっていることは、基本的にはお客様企業の採用活動のサポートですが、採用関連でやるべきことが爆発的に増えているのに、人事部の規模は縮小傾向なんですよ。だからこそ、できる限り採用活動をお手伝いしていきたい、というところが当社単体でのミッションです。グループ全体として考えるなら、やはりお客様企業が人材を確保しなければ生き残れない今の時代に、何としてでも人材確保する方法を提供していく、ということが仕事です。
適材適所の人材確保こそが企業の生きる道
ー斎藤さん自身、今後アナリストとしてどんなことをしていきたいか、展望などお聞かせください。
人手不足に関しては、大手シンクタンクなども発表しているのですが、2030〜2035年の段階では簡単に解決していないだろうと。だからと言って、人材の数を確保できればいいわけでもなく、また人材の質だけでもありません。大事なのは適材適所。トップレベルやオーバースペックの人ではなく、適正な人材を確保できる会社がこの先を生き残れると考えます。お客様が必要としている適材適所をいかに実現していくかが、一層重要になるということ。伴走型のサービス提供会社として、天職市場は一定の評価をいただいており、それは自信にもなっているのですが、これからさらに多様な方法を提供していきます。
今後はタレントプールも必要になってきますし、企業のスター社員を広くアピールするようなやり方も、おそらく人事部の役割となるでしょう。そういった広報などのサポートにも関わりたいですね。
個人としては、とにかく時代の変化を素早く掴むこと。政策関連や人事雇用のトレンドは、2年半くらいのスパンで変化したりするので、その情報を皆さんがキャッチアップするお手伝いができればと考えています。
プロフィール

斎藤一 氏
株式会社天職市場 アナリストチーム
チーフアナリスト
システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。
ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。天職市場YouTubeチャンネルでも情報発信中。